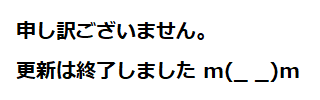音楽が主題になっている漫画はどうしても実感に欠けてしまいがちだと思うのですが、一条ゆかり先生の漫画は表情も豊かで背景に描かれるさまざまな植物画で読んでいるうちに音楽が聞こえてくるような躍動感があります。
生粋のお嬢様である麻見史緒と前世になにかあったのではと思う位不幸な生い立ち、さらに現世でも不幸な少女である緑川萌が前巻まででは予想もできなかったような感情の溶解を見せてページをめくる度に人間性の深みにわくわくしました。
とくにお母さんとの不仲、そして悪役として描かれていた萌のお母さんが、実は伝わりにくい愛情でていたらくに見えていたのも本当のところ萌に父親を持たせたいという願望からだったというのには、衝撃をうけました。
シングルマザーでなくとも、子育てをしていると金銭事に敏感になってしまう母親はたくさんいるでしょう。
「金にがめつい」「男にだらしない」「娘の人生に迷惑をかけっぱなし」と毒親の代表のようなお母さんが、自身を投げ出して萌をかばう、そして直後の死、という展開はこの漫画のサイドストーリーなのかもしれませんが、心にぐっと来るものがありました。
気丈な女性として成長してくる主人公のしおは、さすが大御所先生の画力で1巻からほぼ絵柄は変わっていないものの、ストーリーを意識しすぎているからかだんだん凛々しくなっているように思えて来ます。
あくまでお嬢様として育った「プライド」がしみ込んでいる彼女のキャラクターに覇気が増すのがこの最終巻の後半です。
泣いたり落ち込んだりしていた過去が嘘かの様に、ビシッと決める台詞が次々と発言されているのに、なぜか雰囲気は初巻からあるお嬢様のままで、落ち込んでいたキャラクターを他の巻で見ていたのに違和感を全く感じませんでした。
最後の最後までおなじ音楽グループのピアニストと一緒になるのでは?と予測が付かなかったので、最後まで読んですっきり感が倍増しました。
ストーリーが終わって、続編で神野隆目線のストーリーが足されていて、結婚の後の様子をかいま見れた事も長編であるプライドを読み終わってさらに余韻に浸れます。
好きな人と元歌のライバルの子供を育てるという驚愕的なエンディングも、ライバルとの邂逅がリアルに描かれているのですんなりと受け入れられました。
主人公のキャラクター設定が一貫してぶれが無かったのために「私が育てる!」と言い切った彼女の言葉に重みと信用が自然と付随してきたからです。
繊細で綺麗な絵の合間に簡易な作画で心情を表していたり、気持ちを打ち明ける登場人物はアップでリアルな作画だったりと登場人物が読者と真摯に対応している錯覚に陥る程引き込まれる最終巻です。